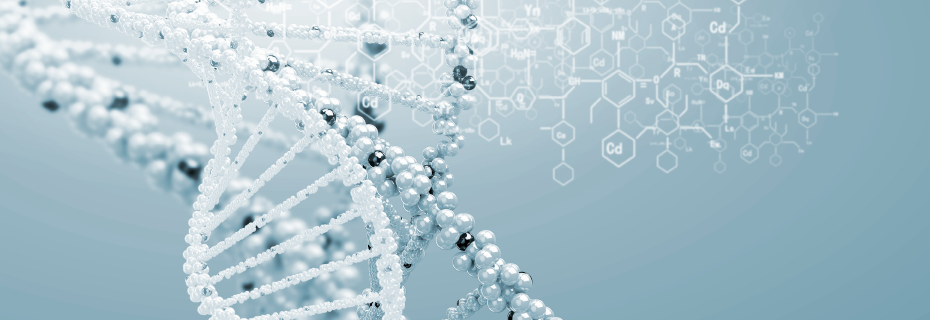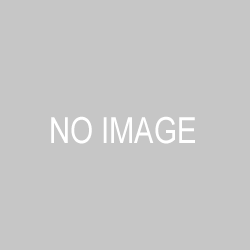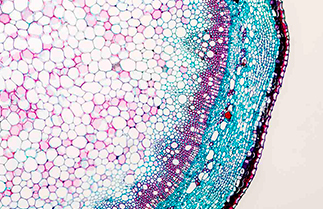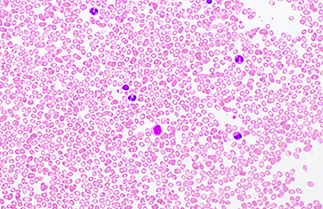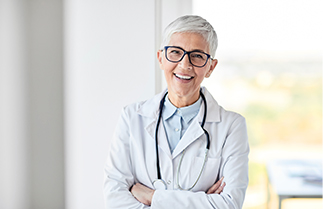健康診断で異常を指摘された方、生活習慣の見直しをお考えの方へ
「血糖値が高めと言われた」「血圧の薬を飲んでいるけど、見直したい」「体重がなかなか減らない」など、健康に不安を感じることはありませんか?
糖尿病・高血圧症・脂質異常症・高尿酸血症などの生活習慣病は、自覚症状が少ないまま進行し、動脈硬化や心筋梗塞・脳卒中など重大な疾患につながることがあります。
当院では、虎ノ門エリアの内科クリニックとして、生活習慣病の早期発見・コントロール・再発予防に力を入れています。医師による丁寧な診察と検査をもとに、患者様お一人お一人の体質・生活背景に合わせた治療と生活改善をご提案します。
糖尿病
■ 以下のような症状がある方はご相談ください
喉が渇きやすい、水をよく飲む
尿の回数や量が多い
食べているのに体重が減る
疲れやすく、集中力が続かない
健診で血糖値やHbA1cが高いと指摘された
■ 糖尿病の原因となる主な病態
インスリン抵抗性(特に2型糖尿病)
筋肉や肝臓、脂肪組織がインスリンに反応しづらくなり、血糖値をうまく下げられなくなる状態。肥満や内臓脂肪の蓄積、運動不足などが主な原因となる
インスリン分泌の低下
膵臓のβ細胞が十分にインスリンを分泌できなくなると、血糖値の調整が難しくなる。一般的に、2型糖尿病ではインスリン分泌低下とインスリン抵抗性が同時に進行する
過食・高糖質な食生活
糖質の多い食事や甘い飲み物、間食などを頻繁に摂る生活は、血糖値の上昇とインスリン分泌の負担を増やし、糖尿病の発症リスクを高める
肥満(特に内臓脂肪型肥満)
お腹まわりに脂肪がつく内臓脂肪型の肥満は、インスリンの働きを妨げる物質を分泌し、糖代謝を悪化させる。BMIが正常でも腹囲が大きい場合は注意が必要
運動不足
筋肉は血糖を消費する大きな器官であり、運動不足になると血糖を取り込む力が弱まり、インスリンの効きも悪くなる
遺伝的要因・家族歴
2型糖尿病は遺伝的要素が強く、家族に糖尿病の方がいる場合は、発症しやすい体質を受け継いでいる可能性がある
加齢
年齢とともに代謝や膵臓の機能が低下し、血糖のコントロールが難しくなる傾向がある
ストレスや睡眠不足
強いストレスや睡眠の質が悪い生活が続くと、血糖値を上昇させるホルモン(コルチゾールなど)が多く分泌され、糖尿病の発症や悪化に関係することがある
膵臓の病気・ホルモン異常による糖尿病(続発性糖尿病)
慢性膵炎や膵がんなどの膵臓の疾患、またはクッシング症候群や甲状腺疾患、褐色細胞腫などのホルモン異常が原因で、糖尿病が発症することがある
薬剤性糖尿病
一部の薬剤(ステロイド、免疫抑制剤、抗精神病薬、利尿薬、インターフェロン製剤など)は、インスリン抵抗性や分泌障害を引き起こし、糖尿病を誘発することがある
妊娠糖尿病
妊娠中に初めて発見される糖代謝異常。妊娠に伴うホルモンの影響でインスリンの働きが妨げられ、血糖値が上がりやすくなる。出産後に改善することが多いものの、将来の2型糖尿病のリスクが高くなるため、継続的な管理が大切
【当院で可能な検査・対応】
血糖・HbA1c・GA・1,5-AGの評価
尿糖・尿たんぱく・微量アルブミン尿検査(糖尿病性腎症のスクリーニング)
食事・運動療法の指導
経口薬・インスリンなどの治療方針提案
合併症の早期発見のための定期フォロー
高血圧症
■ 以下のような症状がある方はご相談ください
健診で血圧が高いと指摘された
朝起きたときに頭が重い、頭痛がする
動悸やめまい、耳鳴りを感じることがある
ストレスを感じると血圧が上がる
家族に高血圧の人がいる
■ 高血圧症の原因となる主な病態
塩分の過剰摂取
塩分(ナトリウム)を摂りすぎると、血液中の水分量が増えて血圧が上昇する。日本人の高血圧の最も重要な要因のひとつ
肥満(特に内臓脂肪型肥満)
体重が増えると血液を全身に送るために心臓に負担がかかり、血圧が上がりやすくなる。また、内臓脂肪によるホルモン異常も関係する
運動不足
身体活動の低下により血管の柔軟性が低下し、自律神経のバランスも乱れて血圧が上がる原因となる
過剰な飲酒・喫煙
アルコールは交感神経を刺激して血圧を上昇させ、タバコは血管を収縮させて一時的な血圧上昇を引き起こす
ストレス
精神的ストレスが続くと交感神経が活性化し、血管が収縮しやすくなり、血圧上昇の原因となる
遺伝的要因・家族歴
高血圧は遺伝的要素も強く、両親や近親者に高血圧の方がいる場合、発症リスクが高まる
加齢
年齢を重ねると血管の弾力が低下し、動脈硬化が進行することで自然と血圧が高くなりやすくなる
睡眠時無呼吸症候群(OSA)
睡眠中の無呼吸により、低酸素状態と交感神経の亢進が繰り返され、慢性的な血圧上昇につながることがある
内分泌疾患(続発性高血圧)
原発性アルドステロン症、クッシング症候群、甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫などは、ホルモン異常によって血圧が上がる「二次性高血圧」の原因となる
腎疾患(慢性腎臓病など)
腎機能が低下すると水分・ナトリウムの排出がうまくいかず、血圧が上昇することがある
【当院で可能な検査・対応】
血圧測定(随時・家庭血圧の管理指導)
血液・尿検査(腎機能・ホルモン異常のスクリーニング)
心電図検査
降圧薬の選定と副作用管理
減塩・運動・ストレス管理などの生活指導
脂質異常症
■ 以下のような症状がある方はご相談ください
健診でコレステロールや中性脂肪の異常を指摘された
運動不足や食生活の乱れが気になる
家族に高脂血症や心筋梗塞の既往がある
甘いものやアルコールをよく摂る
肥満や内臓脂肪が気になる
■ 脂質異常症の原因となる主な病態
食生活の乱れ(高脂肪・高糖質食)
動物性脂肪(飽和脂肪酸)や糖質の過剰摂取により、中性脂肪や悪玉コレステロール(LDL)が増加しやすくなる
運動不足
身体活動の低下により、善玉コレステロール(HDL)が減少し、中性脂肪が増加する傾向がある
肥満(特に内臓脂肪型肥満)
脂肪細胞からの炎症性物質やホルモンが代謝に悪影響を与え、LDLや中性脂肪を上昇させる
アルコールの過剰摂取
中性脂肪を増加させ、脂質異常症のリスクを高めます。特に空腹時の飲酒は悪化要因になる
遺伝的要因(家族性高コレステロール血症など)
生まれつきLDLコレステロールが高くなる体質をもつ人もおり、若年でも心筋梗塞などのリスクが高くなる
糖尿病・インスリン抵抗性
インスリンの働きが悪くなることで、肝臓での脂質代謝に異常が生じ、中性脂肪の増加・HDLの低下を招く
甲状腺機能低下症
基礎代謝が低下することにより、血中のコレステロール値が上昇することがある
ネフローゼ症候群・慢性腎臓病
タンパク尿や腎機能障害に伴って、血中コレステロールや中性脂肪が異常に増加することがある
薬剤性
利尿薬、ステロイド、経口避妊薬、免疫抑制剤などの一部の薬剤が、脂質異常を引き起こすことがある
【当院で可能な検査・対応】
血液検査(LDL・HDL・中性脂肪・non-HDLコレステロールなど)
動脈硬化のリスク評価
生活習慣の見直しと栄養指導
スタチン系薬剤・フィブラート系などの処方
継続的なモニタリングによる数値管理
動脈硬化
■ 以下のような症状がある方はご相談ください
歩くと足がしびれる、休むと治る
血圧・血糖・脂質の異常が複数ある
突然の胸痛や息切れを感じたことがある
脳梗塞や心筋梗塞の家族歴がある
喫煙習慣がある、または過去にあった
■ 動脈硬化の原因となる主な病態
高血圧症
血管に持続的に高い圧力がかかることで、血管内皮が傷つき、動脈硬化が進行する
糖尿病・耐糖能異常
高血糖により血管内皮が損傷しやすくなり、酸化ストレスや慢性炎症を引き起こして動脈硬化を促進する
脂質異常症(高LDL・低HDL・高中性脂肪)
血中に余分な脂質が蓄積し、血管壁にプラーク(粥腫)を形成する。特にLDLコレステロールが高いとリスクが大きくなる
喫煙
一酸化炭素やニコチンによって血管内皮が障害され、血栓形成が促されます。非喫煙者に比べて心筋梗塞や脳卒中のリスクが大きく上昇します。
慢性腎臓病(CKD)
尿毒素やカルシウム・リン代謝異常が血管石灰化を促し、動脈硬化の進行に関与する
メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)
インスリン抵抗性や脂質異常、高血圧を背景に、複合的に動脈硬化のリスクが高まる
加齢
年齢とともに血管の弾力が失われ、自然と動脈硬化が進行しやすくなる。
ストレス・睡眠障害
自律神経の乱れが血圧やホルモンバランスに影響を与え、動脈硬化を悪化させることがある。
【当院で可能な検査・対応】
血液検査(動脈硬化指標・炎症マーカー)
食事療法・運動療法の指導
高リスク例は循環器専門医へ紹介
高尿酸血症・痛風
■ 以下のような症状がある方はご相談ください
足の親指の関節が急に腫れて激しく痛む
関節に赤みや熱感がある
健診で尿酸値が高いと言われた
ビールや肉類をよく摂る
腎機能や尿路結石に不安がある
■ 高尿酸血症・痛風の原因となる主な病態
尿酸の産生過剰によるもの
白血病・悪性腫瘍(がん)、溶血性貧血・多血症、遺伝性代謝異常、肥満や激しい運動
尿酸の排泄低下によるもの
慢性腎臓病・腎不全、利尿薬、一部の降圧薬(サイアザイド系利尿薬など)、脱水、乳酸アシドーシス
生活習慣や食事の影響
プリン体の過剰摂取(肉類、レバー、魚卵、干物、ビールなど)、アルコールの多飲、肥満・メタボリックシンドローム
その他の関連疾患
高血圧症・糖尿病・脂質異常症など
【当院で可能な検査・対応】
血液検査(尿酸値・腎機能・炎症反応)
痛風発作時の薬(NSAIDs、コルヒチン等)の処方
尿酸値を下げる薬(フェブキソスタット・アロプリノール等)の処方
食事・飲酒習慣の見直しと栄養アドバイス
肥満症
■ 以下のような症状がある方はご相談ください
BMIが25以上、腹囲が基準値を超えている
体重増加が止まらない、減量してもすぐ戻る
睡眠中のいびきや無呼吸がある
階段を上るとすぐに息が切れる
血糖・血圧・コレステロールに異常がある
■ 肥満症の原因となる主な病態
過食・高カロリーな食生活
脂質・糖質に偏った食事や、間食・外食の頻度が多い生活は、摂取エネルギーが消費エネルギーを上回り、体脂肪が蓄積されやすくなる
運動不足・活動量の低下
デスクワーク中心の生活や運動習慣の欠如は、基礎代謝の低下や消費エネルギー不足につながり、体重増加を引き起こす
遺伝的要因
肥満になりやすい体質は遺伝的にも影響を受ける。特に両親が肥満体型である場合、生活習慣に注意しても太りやすい傾向がある
ホルモン異常
甲状腺機能低下症、クッシング症候群、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などの内分泌異常は、代謝低下や脂肪の蓄積を促進することがある
ストレス・心理的要因
慢性的なストレスやうつ症状は、食欲の乱れや過食行動を引き起こし、肥満につながることがある。ストレスによる「コルチゾール」の増加も関係する
睡眠不足・不規則な生活リズム
睡眠時間の不足は「レプチン(食欲抑制ホルモン)」の低下、「グレリン(食欲増進ホルモン)」の増加を招き、食欲が増して体重が増加しやすくなる
加齢による基礎代謝の低下
年齢を重ねるにつれて筋肉量が減り、基礎代謝が落ちることで、若い頃と同じ食生活でも太りやすくなる
薬剤性肥満
ステロイド薬、抗うつ薬、糖尿病治療薬(インスリンなど)など、一部の薬剤は体重増加の副作用があることがある