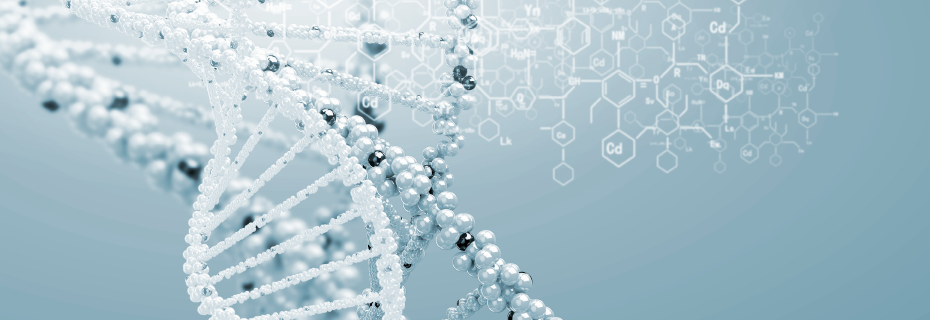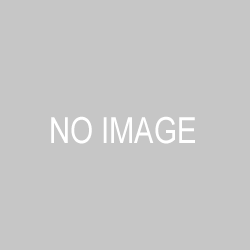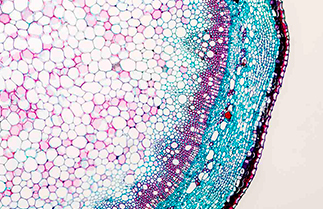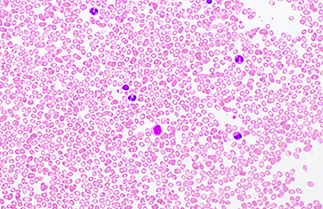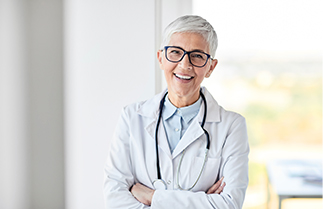通常の健康診断では「基準範囲内=異常なし」と判断されがちですが、それだけでは本当の健康状態は見えてきません。
オーソモレキュラー医学では、細胞が最適に機能するための栄養状態を目指し、一般的な基準値とは異なる「理想値(Optimal Range)」を重視します。
基準値と理想値の違いや、臨床判断に必要な検査値の読み方についてご紹介します。
基準値・病態識別値・治療目標値・臨床判断値の違い
基準値
基準値とは、健常者を対象に統計的に求めた、一般的に「正常」とみなされる範囲を指します。 およそ95%の人がこの範囲に収まるよう設定されており、疾患の有無にかかわらず幅広い集団のデータに基づいています。
病態識別値
病態識別値は、特定の疾患の診断を目的として、専門学会や専門家集団が定めた検査基準です。
例:
- 日本糖尿病学会の診断基準
- 日本痛風・核酸代謝学会の診断基準
治療目標値
治療目標値は、治療開始の判断基準、あるいは治療の到達目標となる検査値です。
例:日本動脈硬化学会のガイドラインに基づく脂質管理目標値
臨床判断値
臨床判断値とは、同じ血中成分でも検査目的によって解釈基準が異なる数値です。 基準範囲とは異なり、疾患リスク、治療経過の評価、予防的介入など、臨床的な判断に用いられます。
オーソモレキュラー医学が重視する「理想値(Optimal Range)」も、広義の臨床判断値にあたります。
性差・個体差について
性差による検査値の違い
男女で、正常範囲や変動傾向に違いが見られる検査項目があります。
【男性優位に高い項目】
- 赤血球数
- ヘモグロビン濃度
- ヘマトクリット値
- プレアルブミン
- ハプトグロビン
- 尿酸
- BUN(血中尿素窒素)
- クレアチニン(Cr)
- 総ビリルビン
- VLDL(超低密度リポ蛋白)
- γ-GTP
- フェリチン
- CPK(クレアチンフォスフォキナーゼ)
- 17-KS(17ケトステロイド)
- カテコールアミン
- アドレナリン
【女性優位に高い項目】
- 血沈(赤血球沈降速度)
- ZTT(硫酸亜鉛濁度試験)
- 中性脂肪(TG)
- IgM(免疫グロブリンM)
- IgD(免疫グロブリンD)
- クレアチニン
- GH(成長ホルモン)
- エストロゲン
- プレグナンジオール
- 黄体化ホルモン(LH)
- プロラクチン
個体差について

上図のように、コリンエステラーゼ (ChE)、ALP、γ-GTPなどの「誘導酵素群」には個体差が非常に大きく、 栄養アプローチの経過によっても予測できない変動を示すことがあります。
個々の患者様の、生活背景、遺伝的要因、ストレス耐性、栄養状態などによって、検査数値の解釈には柔軟な対応が必要です。
一般的な「基準値」vs オーソモレキュラー医学の「理想値(Optimal Range)」の違い
| 基準値 | 理想値(Optimal Range) | |
|---|---|---|
| 目的 | 病気の早期発見 | 細胞レベルの最適な機能 |
| 基準値 | 正常範囲95%を含む | 酵素活性・代謝最適化 |
| 読み方 | 単一項目で異常検出 | 複数項目を関連づける |
| 診断 | 「異常なし」でも見逃しあり |
「未病」「体調不良」を察知 |
具体的な「理想値」の例と読み方
| 項目 | 一般基準値 | 理想値(Optimal Range) | 意味・読み方 |
|---|---|---|---|
| フェリチン(女性) | 5〜150 ng/mL | 50〜100 ng/mL以上 | 鉄貯蔵量。疲労・肌荒れ・冷えなどと密接に関連。 |
| CRP | <0.3 mg/dL | <0.05 mg/dL | 慢性炎症の指標。心血管リスクとも関連。 |
| MCH | 27〜34 pg | 32〜33 pg | 赤血球の成熟度。鉄・ビタミンB群などと関係。 |
| 尿酸 | 3.6〜7.0 mg/dL | 4.0〜6.0 mg/dL | 抗酸化物質として作用。 |
| Alb/グロブリン比 | 1.2〜2.2 | >1.5 | 栄養状態と慢性炎症リスクの評価。 |
TG/HDL比と心血管リスクについて
- TG(中性脂肪)÷ HDLコレステロールの値を計算します。
- 理想値:<2.0
- 2.0以上になると、インスリン抵抗性、脂質異常、動脈硬化リスクが上昇します。
TG/HDL比は、単純なコレステロール値よりも
- 血管内皮障害
- 慢性炎症
- 内臓脂肪蓄積リスク をより的確に反映します!
TG/HDL比が低下することで →「生活習慣病リスクが大きく減る」ことが期待できます。
酸化ストレスマーカーについて
酸化ストレスは、「老化」「生活習慣病」「動脈硬化」「がん」「慢性疲労」の根源です。 これらに対して、オーソモレキュラー医学では、次のような指標をチェックします。
| 項目 | 意味 | 目標値・理想範囲 |
|---|---|---|
| CRP | 慢性炎症マーカー | <0.05 mg/dL |
| γGTP | 活性酸素ストレスと関連 | 最適30未満 |
| 尿酸 | 抗酸化物質 | 4.0〜6.0 mg/dL(極端な低下・上昇は問題) |
| Alb/グロブリン比 | 慢性炎症 vs 栄養状態 | >1.5 |
また、酸化ストレスが強い場合には、
- カタラーゼ活性低下(鉄不足のサイン)
- ビタミンC不足(皮膚バリア低下) なども併発していることが多いため、総合的に読み取る必要があります。
【実際の症例紹介】
症例①:慢性疲労と鉄不足(フェリチン低値)
患者背景 30代女性、慢性的な倦怠感、めまい、爪の割れ、動悸を訴え来院。 一般健康診断では「異常なし」。
検査結果
- フェリチン 12 ng/mL(基準値内だがOptimal未満)
- MCV低値、MCH低値
- 亜鉛も不足気味
対応 鉄サプリメント(吸収性に優れたヘム鉄)と亜鉛補充開始。ビタミンC併用。
結果 2ヶ月後、フェリチンが70 ng/mLに到達。
- 倦怠感ほぼ消失
- 爪の状態改善
- 運動後の回復もスムーズに
症例②:TG/HDL比の改善でメタボリスク低下
患者背景 40代男性、BMI28、軽度脂質異常症。 一般診断では「やや高め」とのみ指摘。
検査結果
- TG/HDL比:3.5(リスク高)
- CRPも0.2(軽度慢性炎症あり)
対応 糖質制限、EPAサプリ導入、有酸素運動。
結果 3ヶ月後
- TG/HDL比:1.5に改善
- 体重−5kg
- CRPも0.05に低下
→ 動脈硬化進行リスクの大幅低下!
オーソモレキュラー医学では、単に病気を防ぐだけでなく、細胞が最適に機能する「本当の健康状態」を目指します。 一般的な検査基準にとらわれず、理想値(Optimal Range)を意識することで、より早期に体調不良や未病の兆候に気づくことが可能です。
TG/HDL比や酸化ストレスマーカーなど、複数の検査データを総合的に読み解きながら、隠れたリスクにいち早くアプローチしていきます。
数値を単体で評価するのではなく、複合的なデータ解釈と、生活習慣・栄養への具体的なアプローチを組み合わせることが、真の健康への鍵となります。
「なんとなく不調」を感じている方へ 私たちと一緒に、数値の奥に隠れた身体からのサインをひも解き、より良い健康を目指していきましょう。